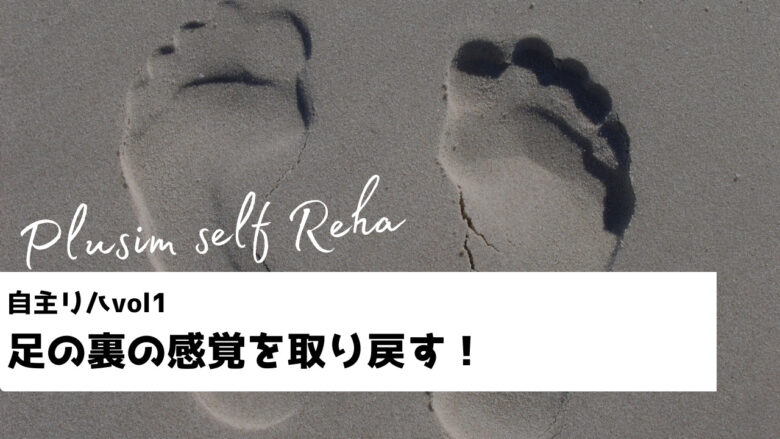足の裏の感覚は歩行や立ち上がりに必要不可欠!
脳出血や脳梗塞の後遺症に【感覚障害】があります。発症した脳の場所によって感覚障害が見られる体の場所は異なりますが、足の裏が感じにくくなるケースは非常に多いです。
運動障害と比べると歩く・立つの動作獲得のリハビリでの優先度は低く思われがちですが、全くもってそんなことはありません。
例えば足の裏の感覚がわからないと次のようなことが生じます。
支えている感じがわからないため
どれくらい体重が乗っているかわからないため
床や地面の感じがわからないため
もしこれらの症状がみられたら、それは足の裏の感覚が原因かもしれません。そんなあなたに足の裏の感覚が感じやすくなる自主リハビリをご紹介します!
まずは足の裏に触れてる感じから
1つ目の自主リハビリは、感覚のベース【触れるのがわかるようになる】を目的に行います。足の裏が床に着いてるのかどうか、また着いているのがわかりやすいのはどこかを知っていきましょう。
できれば背もたれなしがオススメです
固いものを使用してください
踏みつけないように注意!
頭の中で足の裏をイメージして場所を確認します
- ゆっくりと乗せるだけで絶対に踏みつけない!
触れている感覚が大切です。踏みつけてしまうと別の感覚になってしまうので気をつけてください。
- 予測が大切!
できれば置く前に足の裏のどの辺に物が来るのかを想像して、物が当たるところに集中しながら足を物に乗せると、より効果が出やすいです。
- 声に出してみる
足をゆっくりとおろしていくときに、足の裏のどこかが床に着いたら「今、〇〇が床に着いた」と口にだすと、感覚がわかりやすくなってきます
体重の量を足の裏で感じる
2つ目の自主リハビリは、足の裏の感覚の大切な役割【体重が乗っている量がわかる】を目的に行います麻痺側の足の裏の感覚だけでは判断せずに、非麻痺側の足の裏の感覚も感じながら体重を均等に載せれるようになりましょう。最終的には、安心して麻痺側に体重をのせれるようになることを目指します。
安全な場所で行なってください
非麻痺側に体重を乗せたところから、少しずつ麻痺側に体重を移動する
麻痺側の足の裏に体重が乗ってくる感じに集中する。わからない場合は、非麻痺惻の足の裏の体重が減っていく感じに集中する
左右にゆっくりと体重移動を繰り返して、体重の増減を足の裏で感じる
- 非麻痺側を参考に!
非麻痺側の足の裏の感覚を参考に麻痺側の感覚に集中してみてください
「これくらい体重移動したから、こんな感じがするはず…」みたいな感じです - 速さよりも正確さ
体重量の変化を感じられるようになりたいので、ゆっくりと行なってください
- 安全第一
立っているときにふらつく場合は、何かにつかまって行なってください
感覚のリハビリは専門家にお任せください
リハビリにはいろいろな方法がありますが、プラシムでは感覚障害に特化した内容を行なっています。
筋力トレーニングや動作練習だけでは改善できない領域を新しいリハビリで目指しませんか?