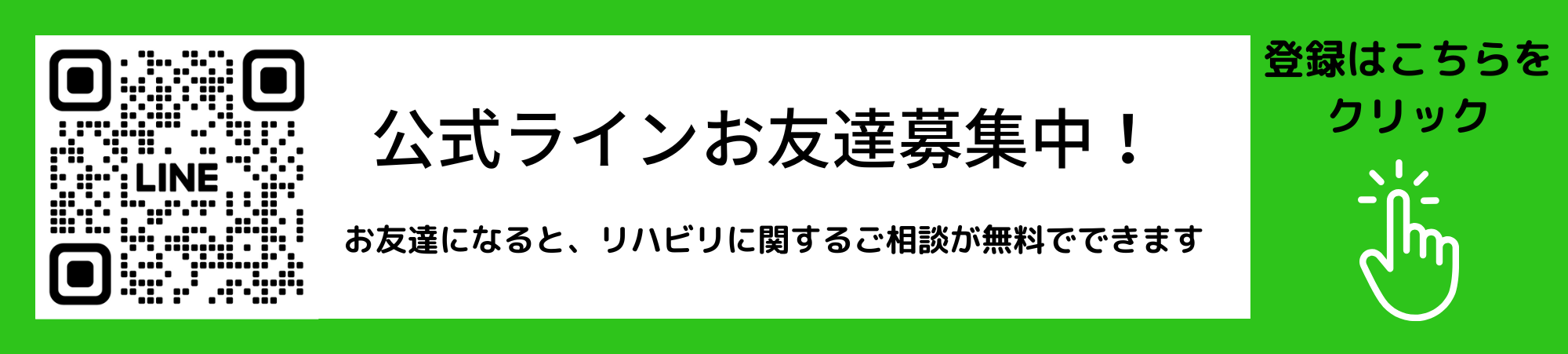再発について
脳梗塞再発のリスク・傾向
脳梗塞は再発しやすい疾患です。日本国内・国外の報告を含め、再発率についてご紹介します。
- 「日本における脳梗塞の再発率は、1年間で約3.8 %」、10年追跡で累積再発率が 49.7 % に達するという報告もあります。(鳥谷、2020)
- 医書レビューでは、脳卒中全体で年間再発率は約5 %(=20人に1人)という見積もりがあり、10年間で約半数が再発する可能性を指摘しています。(平野、2019)
- 病型別再発率として心原性脳塞栓症19.6 %、アテローム血栓性梗塞14.8 %、ラクナ梗塞7.2 %と報告されています。(冨元、2018)
- 日本の回復期リハビリテーション期における再発例調査では、入院中に再発転院となった例が 1,301例中16例(1.2 %程度)あったという報告もあります。(萩原、2013)
これらから見えることは、脳梗塞後は長期にわたって再発のリスクが持続するという点です。そのため日々の生活の中で再発の予防に良いことを継続できるかが重要なポイントになります。
どうして再発するのか?(リスク要因とその背景)
再発が起きる背景には多くの共通リスク因子が関与します。以下に整理します。
| リスク因子 | 内容・メカニズム | 日本の知見・注意点等 |
|---|---|---|
| 高血圧 | 血管壁への負荷、内皮機能障害、動脈硬化促進 | 冨元(2018)は、降圧療法が再発抑制の中心であり、ガイドラインでは少なくとも140/90 mmHg未満を目標とすることを勧めると報告しています。 |
| 脂質異常(高LDLなど) | プラーク形成、プラーク不安定化 → 血栓形成 | 平野(2019)は危険因子管理の柱であると報告しています。 |
| 糖尿病・高血糖 | 血管内皮障害、微小血管障害など | 冨元(2018)は、糖尿病管理は必要だが、高血圧管理の方が優先度が高い可能性についても言及しています。 |
| 心原性因子(特に心房細動など) | 心臓内にできた血栓が脳へ飛ぶ(心原性塞栓) | さらに心原性脳塞栓症は再発率が他より高いと報告されています。 |
| 動脈硬化・プラーク | 頸動脈・頭蓋内動脈・内頸動脈の狭窄など | 再発予防では、狭窄部位やプラーク進展をモニタリングすることの重要性も指摘されています。(平野、2019) |
| 生活習慣(喫煙・飲酒・肥満・運動不足) | 上記の因子を悪化させ、血管・代謝系を破綻させる | 過度の飲酒・塩分摂取・食生活などの改善が推奨されています。 |
| その他 | 血液凝固異常、炎症、慢性腎疾患、薬剤不遵守、認知機能低下など | 自己効力感・家族支援・自己管理行動との関連が示されています。(山口、2012) |
これらからさまざま要因が影響していることがわかります。これは一人一人リスク因子が異なり、生活内で気をつけなければならないことが異なることを示しています。
再発を予防するために
再発を防ぐには、複数の手段を統合して取り組むことが不可欠です。以下に具体的な方法のポイントを整理します。
危険因子管理
血圧コントロール
- 降圧療法が再発抑制の中心軸であり、目標血圧として少なくとも 140/90 mmHg 未満を目指すべきと述されています。(冨元、2018)
- 主幹動脈狭窄や内頸動脈狭窄などを有する患者では、過度な降圧による脳血流低下のリスクも考慮すべきだとされます。
- また平野(2019)は再発予防の二本柱として「危険因子の徹底管理と適切な抗血栓療法」が挙げられています。
- これらに年齢、腎機能、既存の合併症も考慮して個々人に適した目標血圧を設定することが重要です。
抗血栓療法
- 脳梗塞再発予防では、抗血栓療法(抗血小板薬、抗凝固薬など)も非常に重要な戦略と位置づけられています。
- ただし、出血リスクとの兼ね合いが常に問われ、使用開始・中止・併用の判断には注意が必要です。(平野、2019)
生活習慣改善
- 食事(減塩・バランス食)、適度な運動、節酒・禁煙が重要です。
- 例えば、食塩摂取量を1日1g減らすと、収縮期血圧を約1 mmHg下げることが期待できます。
- 在宅軽症脳梗塞患者を対象とした研究では、自己効力感が高い患者は脂質制限や運動を実践しやすい傾向があるとの報告もあります。(山口、2012)
自己管理・教育・フォローアップ体制
- 日本の再発予防介入研究(厚生労働省助成)では、急性期退院後 6か月以内の脳梗塞・TIA患者を対象とした保健指導プログラムによる無作為化比較試験を実施しており、再発予防の可能性を検討しています。
- また「回復期リハビリテーション病棟における脳卒中再発予防患者教育」に関する全国調査も報告されており、入院中からの教育介入の有無・実践状況を把握する研究もあります。(木下、2015)
- 退院後、患者が自己目標を設定することで再発予防行動へつながる可能性を検討した研究もあります。(植西、2024)
これらから医療機関だけでなく患者さん本人・ご家族が主体的に関わる体制づくりが重要であることがわかります。
再発とリハビリテーション
予防に役立つリハビリ
- 運動・身体活動を通じた代謝改善
リハビリを通じて筋力・持久性を高め、運動習慣を定着させることで、血圧・血糖・脂質などの改善につながり再発リスク因子を抑えられます。 - 神経可塑性・代償メカニズムの促進
運動刺激を通じて脳の再構築(可塑性)が誘発され、機能制御系を改善する可能性があります。 - 早期介入・継続性の重要性
早期から始めることで、機能低下の進行・合併症(拘縮、運動不活性による血管リスク悪化など)を防止でき、長期的な健康維持につながり得ます。 - モチベーション・自己効力感の向上が自己管理につながる
リハビリを通じて「自分で動く」経験を重ねることが、自己効力感を高め、薬物療法や生活習慣改善の継続性が期待できます。
※ リハビリ単独ではなく薬物療法・リスク管理との併合が不可欠です。
リハビリ実施の注意点・工夫
- リハビリ開始は継続して行う。
- 強度・頻度を確保し、個別化したプログラム設計を行う。
- 患者の全体的な体調(心血管リスク、骨関節状態、出血リスクなど)を考慮しながら運動負荷を調整する。
- リハビリ中も定期的なモニタリング(血圧、心電図、症状変化など)を行い管理する。
- 在宅リハビリやセルフ訓練プログラム、家族支援も併用することで継続性を保つ。
まとめ: “再発防止の要点”
まとめ:“再発防止の要点”
- 脳梗塞は再発しやすい疾患であり、1年~10年追跡では相当数の患者に再発が認められます。
- 脳梗塞再発を防ぐには、危険因子管理(血圧、脂質、血糖など)、適切な抗血栓療法、生活習慣改善、自己管理支援・教育、定期フォローアップ体制がすべて揃って初めて効果を発揮します。
- リハビリテーションは、残存機能改善だけでなく、運動習慣化や血管代謝改善、心理面サポートを通じて再発予防も期待できます。
- 患者さん・ご家族としては、自己効力感を高め、教育を受け、自己目標設定・継続行動を支えられる環境をつくることが、長期的な予防にとって大きな力になります。
参考文献
- 冨本秀和, 脳梗塞:これからの再発予防治療, 2018, 日本脳神経血管内治療学会誌
- 萩原のり子, 回復期リハビリテーション期における脳卒中再発症例の検討, 2013, 脳卒中
- 鳥谷めぐみ, 高齢軽症脳梗塞患者の再発に関するリスク認知, 2020, 日本看護学会誌
- 山口幸, 在宅軽症脳梗塞患者の再発予防に向けた自己管理行動と自己効力感,家族の支援行動および家族機能との関連, 2012, 家族看護学研究
- 井上智貴, 回復期リハビリテーション期の脳卒中再発例の検討, 2009, 脳卒中研究
- (助成事業報告)保健指導の導入による脳卒中・心筋梗塞の再発予防効果, (発表年省略), 厚生労働省助成研究報告書