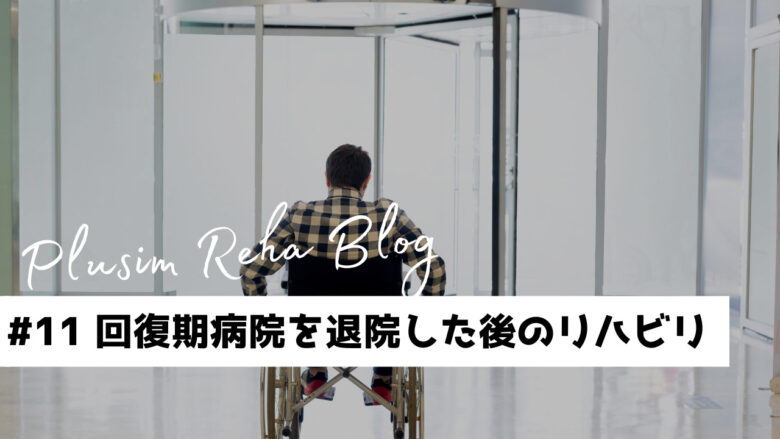「突然手足に力が入らなくなり、救急車を呼んで病院へ行き脳画像を撮影すると【脳梗塞】や【脳(内)出血】とお医者さんに言われました。そのまま入院となりこの先どうすれば良いのかわからないまま、リハビリ専門の回復期病院へと転院…不安でいっぱいでした。」
この話は、私が回復期病院に勤務していた頃に患者さんから聞いた話です。
ある日突然襲ってくる脳卒中は、その日を境に生活を一変させます。
救急車で運ばれる急性期病院やリハビリ目的の回復期病院に入院している間は、整った環境で専門家が近くで見守っているので不安も少なく過ごせます。
ですが自宅へ退院すると、段差があったり手すりがない環境で専門家もいない中で生活していかなければなりません。
そのため、回復期病院を退院するまでに色々と準備しておくことが大切です。
こちらでは回復期病院を退院した後のリハビリや介護サービスの準備の進め方やポイントをご紹介していきます。
入院した回復期病院やお住まいの地域によって多少異なりますので、詳細は病院のソーシャルワーカーや役所の介護課へお聞きください。
入院から退院までの流れ
はじめに、病院の役割である急性期・回復期・維持期(生活期)について簡単に説明します。
治療する段階(急性期)、リハビリする段階(回復期)、生活する段階(維持期・生活期)と表すことができて、患者さんの病状に合わせて提供されるサービスが変化していきます。
1.急性期
脳卒中や骨折後、救急車で運ばれる病院です。主に治療が目的で、症状が安定するまで入院します。
約2週間〜2ヶ月で自宅へ退院か回復期病院へ転院となります。
2.回復期
大腿骨頸部骨折や脳卒中で自宅での生活がまだ難しい場合、生活動作の獲得を目的に入院する病院です。疾患ごとに入院できる期間が決まっており、1日で最大3時間までリハビリできます。
3.維持期(生活期)
病院を退院し、生活がメインとなる段階です。
この頃には、医療保険を使用したリハビリは終了し介護保険を使用したサービスへと移行します。
この過程の中でのポイントをご紹介します。
ポイント1 回復期病院の選び方(急性期病院入院中)
急性期病院から自宅への退院がまだ難しい場合は、リハビリ目的で回復期病院への転院を勧められます。
患者さんの話を聞いていると、病院によって多少紹介の方法が異なるようです。
【急性期病院の近くの回復期病院のリストを渡され、自分で見学に行って決めた】
【自宅の回復期病院を自分で調べて見学に行った】
【急性期病院の系列の回復期病院へ自動で転院となった】
系列病院での自動化された転院ではあまり悩むことはありませんが、自分で決める時にはどこが良いのか悩むと思います。
リハビリの専門家の立場から言えることは、回復期病院を選ぶときに重要なのはリハビリの量です。
1 、何床の病院なのか(回復期病床)
2 、平均入院日数は何日なのか
3 、スタッフは何人いるのか(特に言語聴覚士)
4 、平均提供単位数は何単位か(1日9単位までできる)
回復期病院に入院している時期、はベッドに横になっている時間は少なく、リハビリを行っている時間が多い方が良い時期です。
1日で行うリハビリの量や理学療法士・作業療法士の人数を中心に調べるのがポイントです。
ポイント2 退院後のリハビリ(回復期に入院中)
介護認定(介護保険)
まずは回復期病院に入院している間に介護認定調査を必ず受けてください。
基本的には退院日が決まれば審査を受けることができます。
お住まいに地域によっては入院してすぐ申し込みができる場合もありますので、入院中の病院にいるソーシャルワーカーに相談してみてください。
退院後は介護保険を使用して、訪問介護やデイサービスなど様々なサービスを受けることができます。もちろんリハビリも介護保険を使用するため介護認定は必須です。
ですが40歳未満の方は介護認定が出来なかったり、介護度によって受けられるサービスに制限があるなど介護保険にもいろいろあります。
リハビリにおいても例外ではなく、訪問介護やヘルパー、施設に入居する方は施設を利用するとリハビリが出来ないことも多いです。
そうなると回復期病院を退院した後はリハビリが受けられません。
もっと良くなりたい、生活の質を下げたくない人は介護保険のサービスだけでは難しいです。
そこで知っておいて欲しいのが保険外・自費リハビリです。
保険外(自費)リハビリを利用する目的
すでに説明しましたが退院後に行うリハビリは介護保険を利用して行います。
ですが介護保険でのリハビリはその特性上【量】に強い制限があります。
ヘルパーや訪問介護などのサービスを受けると週に1〜2回しかリハビリができず、その内容もグループで行うリハビリだったりと望んでいるものとは異なると感じる人も多いです。
また年齢によっては介護保険が対象にならない人もいます。
そのため保険を使用しないで行う方法でしかリハビリを受けられない・増やせないのが今の維持期のリハビリです。
保険でのリハビリは10代から90歳を超える方まで非常に幅広く行っていますが、自費の訪問リハビリを行うプラシムをご利用されている方は30歳代〜60歳代の方が多くなっています。
これには次の理由があります。
・年齢の問題で介護保険が利用できない
・介護保険のリハビリでは量が足りないし専門的ではない
・入居中の施設にリハビリがない
ご本人やご家族の強い想いに応えるために、プラシムではあなたの希望を最優先にリハビリを進めていきます。
Plusimでは自宅の近くにリハビリができる場所がない方や外出が難しい方へ、脳卒中などに特化したリハビリが自宅で受けられる【自費の訪問リハビリ】を提供しています。
現在、神奈川県、茨城県つくば市、千葉市県北、新潟県、山形県、福島県で訪問リハビリを行っています。
ご自身のお身体の状態を知りたい方やプロのリハビリを受けたい方は、お気軽にお問い合わせください。
こちらの記事も合わせて読まれています
ご予約・お問い合わせ
プラシム 総合窓口