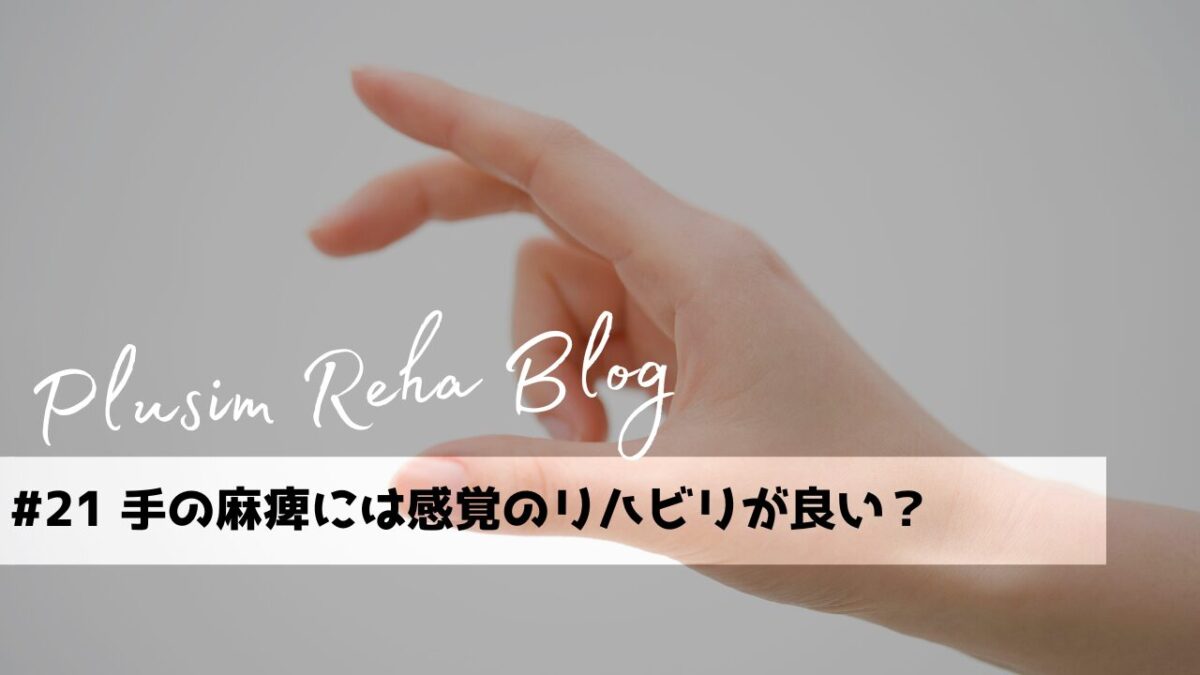こんにちは。理学療法士の唐沢です。
脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)の後遺症で悩まれている原因の多くは運動障害です。手足が動かしにくい・動かない症状で、麻痺が原因の1つに挙げられます。
麻痺による運動障害はご病気の場所によって異なるものの、下肢よりも上肢に現れやすく特に手指の動かしにくさに悩まれている人が多くなっています。
そこで手の麻痺にはどんなリハビリが有効なのかを簡単に紹介しながらプラシムで行っている感覚を通したリハビリを中心にご紹介していきます。
手のリハビリで大切な3つのポイント
ただ動かすから巧緻に動かすへ
手指の動作は非常に複雑
足よりも手は高次脳機能障害の影響を受ける
手の動作には感覚が必須
手触りという言葉があるように、手では感覚がとても重要です。感覚は手指を動かす時にも大きな役割を持っています。
例えば柔らかいものを持つ時と硬いものを持つ時では指先に入る力の量は全く違います。また滑りやすいものと安定しているものでも力の入れ方は変わります。つまり指先の感覚をもとに力の量をコントロールしているのが手の特徴です。
このことから手指のリハビリではただ動かす練習だけでなく感覚を通して動かし方を学習するリハビリがとても大切です。プラシムでは認知神経リハビリテーションをベースとした知覚から運動を学習する方法を行なっています。詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。
手特有の2種類の筋肉
手指を動かす筋肉には2種類あるのをご存知ですか?
1つは肘の近くから指先に付いている【外在筋】もう1つは手の中から始まり手の中に付いている【内在筋】の2つです。実は内在筋に対するリハビリってほとんどないんです。むしろこの2つを分けてリハビリすること自体が珍しいです。
単純に指を伸ばす曲げる練習ではほとんど外在筋しか使われず、つまむなどの細かい動きの獲得には内在筋の働きがとても重要です。そこでプラシムでは指の動きをさらに細かく分析し手指の動作を考慮したリハビリを行なっています。
高次脳機能障害の影響
プラシムは右片麻痺専門のリハビリを提供しています。右片麻痺では失語症や失行症などの高次脳機能障害がみられますが手指の動作に大きな影響を及ぼします。手指の運動麻痺がないのに細かい動作が行えない人は高次脳機能障害が影響しています。
プラシムでは高次脳機能障害のエキスパートが右片麻痺に特化したリハビリを提供しています。言語機能を考慮して脳科学・脳神経科学をベースにプログラムを作成するため確実に改善を目指していきます。